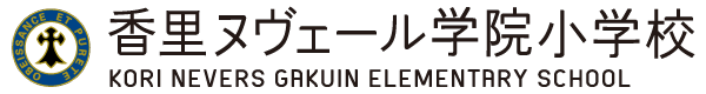ニュース&トピックス
2019年01月31日
「香里ヌヴェールの挑戦」(第15回)
「香里ヌヴェールの挑戦」(第15回)
今回は、香里ヌヴェール学院小学校の「研究授業」がテーマです。
本校では、各学年が年一回、「研究授業」を実施します。
今回は、2年生の算数が選ばれました。
「研究授業」には、「事前研」と呼ばれる、事前に内容に関して担当者が集まって協議する場があります。
各学年で実施しますので、いい意味での競争心が学年団にも芽生えます。
今回も、今年度の研究テーマである、「分析・批判し、対話を通した創造的思考による最適解を考え伝え合う授業の工夫」にそって、意欲的というか、アグレッシブな内容が提案されました。
「創造的」という言葉を盛り込もうとすると低学年はどうしても厳しくなりがちなんです。
今回は、小学校2年生の算数の「箱」が題材として選ばれました。
教科書では、「箱」の仕組みを取り扱っていて、「箱」の今ある箱を展開したり、展開図から組み立てるという内容が盛り込まれています。
そこから一歩発展を学年団は狙います。
異なる4種類の板から「箱」を3つ作ってみようと。
「もの作り」の楽しみを子どもたちにまず体験させたいと。
なるほど、いいですね。
試行錯誤しながら「もの」を作る。
レゴ好きの子どもたちがとても喜びそうです。
そして、もちろんそれで終わりません。
4種類の板は、同じ大きさの板は同じ色なんです。
ここから、完成後何かが得られるのです。
何でしょう。
実は、ここがこの授業の一つの「肝」の部分となっています。
小学校2年生で扱う「箱」は、立方体、直方体と言われる六面体です。
六面体には、何らかの法則があります。
それを見つけて欲しいのです。
それを先生たちは、「ひみつ」と呼びました。
いやはやオモロイです。
算数や数学では、いわゆる公式や定理といったものがあるのは皆さまもご存知だと思います。
公式や定理は、それ自体導かれるプロセスが必ずあります。
まず覚えて、当てはめればいいというものではありません。
どんな「ひみつ」があるのか?
なんかワクワクしませんか。
・・・「香里ヌヴェールの挑戦」(第16回)に続く
「香里ヌヴェールの挑戦」(第14回)はこちら