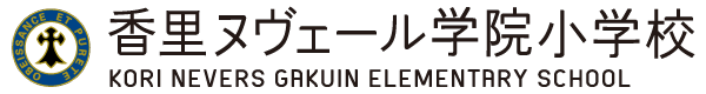ニュース&トピックス
2018年11月28日
「香里ヌヴェールの挑戦」(第7回)
「香里ヌヴェールの挑戦」(第7回)
「Men For Others」
小学校の先生が、どのタイミングかは覚えてないのですが、
この言葉を子どもたちに語っているのを聞きました。
キリスト教の中で根幹となる考え方です。
神様から与えられた命、才能を何のために使うのか、
それに対する明快な言葉だと改めて思いました。
「何のために生きているのか」
「何のために働いているのか」
自分自身、仕事をはじめて30年を過ぎて、
いろいろなことを経験してきました。
自らの成長のために頑張っていたこともあれば、
生徒のためにと思っていたこともあるし、
職場のためにと踏ん張ってきたこともありました。
仕事の役割も現場の教員であり、
広報の担当であり、
中間管理職であり、
そして校長という役割も担いました。
年齢も50を越えて、教員生活も終盤戦を迎える中で、
次はどうしたらいいのかな、
何のために仕事をしていけばいいのかなと思い悩む日々に再び出会った
「Men For Others」という言葉。
自分自身の未来に向けて、一筋の光がそこに明確に見えたのです。
「教育方針」という4文字の重要性。
リーダーともなると、
ビジョンをいかに明快に教職員に示すのかが最も大事だと思います。
とはいえ、悩ましいこともあります。
理想と現実、建前と本音のはざまで常に悩むのです。
『わかりやすく教育内容を説明して、生徒募集を成功に導かないといけない』
『そうは言っても進学実績もないと、私学として認められない』
『新しい教育の取り組みをアピールしないと、話題性に乏しい』などなど、
常に現実と向き合いながら本質は何かと模索し、
中間管理職としてさまよった十数年間が自分にもありました。
本当ですよ、実は。
でも、最後に残るのは「本質」です。
当たり前の事ですが、
先生という「先に生きている」人間からすると、
教育の本質は「先に生きている」ものがいなくなってから、
「後に生きている」生徒たちは生きていかなければならないことです。
となると「後に生きる」人たちに何を残すことが出来るのか?
コンテンツは流行りすたり 、ノウハウは大事だけど、
やはり最後残るものは精神性ではないかと。
「Men For Others」は、
カトリック信者である自分がたどりついた黄金律だったのです。
・・・「香里ヌヴェールの挑戦」(第8回)に続く
「香里ヌヴェールの挑戦」(第6回)はこちら