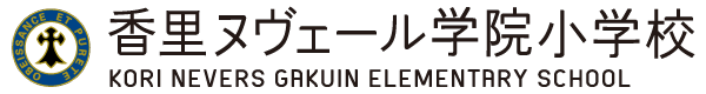ニュース&トピックス
2018年11月9日
「香里ヌヴェールの挑戦」(第4回)
「香里ヌヴェールの挑戦」(第4回)
PBLは「プロジェクトベースドラーニング」を意味します。
定義としては、
「知識の暗記といった受身の学習から脱却し、
自ら問題を発見・解決していく能力を身につけることを目的とする学習」です。
私自身、一冊目の本の略歴から『アクティブラーニングの実践家』という分類をいただくのですが、
アクティブラーニングという言葉が広がるにつれて違和感をもつようになってきました。
アクティブラーニングの違和感とは、
生徒たちが活発に発言するのはいいことですが、
まとまりのない、そしてあまりに根拠もない話が延々と続いていくことでしょうか。
関西的には、「で?」と言われそうなオチのない話になりがちです(笑)
一方、プロジェクトベースドラーニング。
こちらは、オチがないとアキマヘン。
オモロクなくてもいいのですが(笑)
プロジェクトとは、一つのゴールです。
「正解のない問い」が与えられた時に、
アクティブラーニングの場合は、往々にして何も結論を出さずに終わってしまいます。
前回のブログに書いた感じです。
プロジェクトベースドラーニングは、
「問い」に対して「正解」であるかはわからないものの、
「最適解」は必ず出す必要があります。
プロジェクトを達成するためには、どんなことが必要でしょうか。
1. 与えられた「問い」に関して、多くの情報を持っていること。
2. 「問い」に対してどんな解決があるか想像力があること。
3. 2.で想像した仮説を1の情報を組み合わせながら最適解を探す。
といった流れが一つ考えられます。
上記の3点は、個人ワークでもグループワークでも可能です。
グループであれば、
1. グループで最適解を出そうとする「共感」マインド
2. グループで安心して多様な意見を言える安心安全な場
が大事ではないかと思います。
そして、もう一つ最も大事な視点があります。
それは、「クリティカルシンキング」です。
個人でもグループでも、『常に俯瞰してみる力』が必要だと感じています。
「本当にそうなの?」
「違う考えはないの?」
と違う視点からのチェックが必要です。
ちょっと細かく書いてしまいました。
さて、2年前の学院のプロジェクトは、
「21世紀型教育を実践する香里ヌヴェール学院を創る」
でした。
我々は実際に、このプロジェクトに今日もなお取り組んでいるのです。
・・・「香里ヌヴェールの挑戦」(第5回)に続く
「香里ヌヴェールの挑戦」(第1回)はこちら
「香里ヌヴェールの挑戦」(第2回)はこちら
「香里ヌヴェールの挑戦」(第3回)はこちら