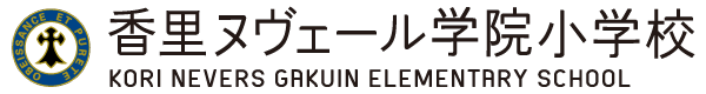ニュース&トピックス
2019年03月6日
「香里ヌヴェールの挑戦」(第20回)
「香里ヌヴェールの挑戦」(第20回)
皆さま、こんにちは。
いよいよ3月、学校は年度末。
師走が忙しいといわれますが、
実はこの時期が一番学校は忙しい時期なんです。
さてさて、そんな話はおいといて、
「そうぞうするチカラ」
あえて「そうぞう」すると書かせていただきました。
さて、これは「創造」ですか?「想像」ですか?
ちょっと調べてみると、
「創造」は「新たなものをつくりだすこと」
「想像」は「現実にないものを思い浮かべること」。
芸術家が、作品を完成させるために、
「イマジネーションを働かせる」という使い方をします。
「創造」と「想像」は分けて考えるものではないかもしれません。
「想像」の先に、「創造」があるのかも、ですね。
PBL(Project Based Learning)に必要な力として、この「そうぞうするチカラ」があります。
正解のない課題に対応するのですから、どうしたらいいのかを考えるチカラが必要です。
すなわち、「想像力」です。
「想像力」とは「発想力」あるいは「思い付き」なのか、かもしれません
「思い付き」って、ゼロからいきなり生まれるのか。
そうではないと考えます。
それまでに獲得した知識や経験が、頭の中を飛び交って出てくるものではないでしょうか。
「想像力」が必要な問題を、今回年中児対象の体験会でやりました。
「ホットケーキを蟻さんと象さんでどうやって分けたらいいですか?」
正解がありそうでない、この問い、算数の学習につながります。
子どもたちは、必死になってこの問いを考えました。
「半分半分にする」 うん、わかります。
「象さんの方が大きいから多めにする」 うん、これもわかります。
「蟻さんは食べて大きくなってもらいたいから大きめにする」
なんと、この発想はオモロイ。
子どもたちは、「等分に」分けることは何らか身に付けている感覚です。
そして、家庭生活で必ずしも、等分に分けることがすべてではないと学んでいたりします。
知識として獲得したり、経験として獲得したり、
「そうぞうするチカラ」は誰にも身につけるチャンスはあるのでは、と思います。
・・・「香里ヌヴェールの挑戦」(第21回)に続く
「香里ヌヴェールの挑戦」(第19回)はこちら