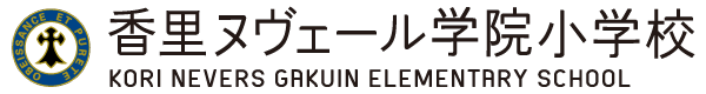ニュース&トピックス
2019年05月8日
「香里ヌヴェールの挑戦」(第31回)
「香里ヌヴェールの挑戦」(第31回)
10連休が終わりました。
いよいよ元号も令和となりましたが、
皆さま、いかがお過ごしでしょうか。
さて、教育の中で長らくその必要性が叫ばれ続けながら、
なかなか実現できてなかったことを考えてみます。
第一は、「使える英語」。
中学校から何年も英語の授業を受けながら、
外国人とろくに会話もできない、と言われてきました。
第二は、「創造性」。
日本人は指示されたことは得意だが、
新しいことを考えたり、創るのは苦手、とも言われてきました。
この二つは、自分が受けた昭和から言われ続けてきました。
内容のニュアンスは異なるとは思いますが、
今日もこの二つは、日本の教育の課題と言われています。
そして、もう一つの課題が、「多様性」です。
この「多様性」ですが、
昭和の時よりも平成において、
その重要性が叫ばれてきたような気がします。
「多様性」という言葉ですが、
その定義が、上記の二つと同じくらいか、
それ以上に難しい言葉かもしれません。
「幅広く性質の異なるものが存在すること」と意味がありますが、
「多様な働き方」
「生物多様性」
「多様なアイディア」
などなど幅広く使われます。
学校現場では、
「多様な生徒」
「多様な考え方・生き方」
なんでしょうか。
「いろいろな在り方、考え方」があってよいと、教育現場では言われてはいます。
しかしながら、
同調圧力が強いのも事実で、
「空気を読まず」、「他人と違う言動」がNGになりがち、
ということはないでしょうか。
「多数決」の大事さは、よくわかりますが、
少数はどうなるのでしょうか。
各自が自ら考え抜いた意見が重なるなら、まだ判りますが、
「多数決」になりそうな「正解?」を探し、
結果「多数」になった意見は、どうなんでしょうか。
「自分とは異なる考えがある」 ことを認め、そこに何かヒントがある。
無理に仲良くする必要もなければ、
異なるからと言って攻撃することもない。
「違い」と普通に同居できる。
そんな居心地のよい場所に学校がなっていって欲しい。
「多様性」という言葉とうまくやっていきたいな、と思う今日この頃です。
・・・「香里ヌヴェールの挑戦」(第32回)に続く
「香里ヌヴェールの挑戦」(第30回)はこちら