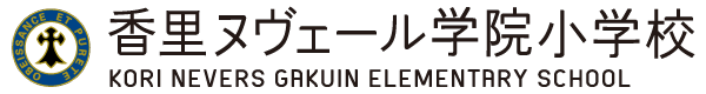ニュース&トピックス
2018年11月5日
「香里ヌヴェールの挑戦」(第3回)
「香里ヌヴェールの挑戦」(第3回)
「津波の影響で、陸に乗り上げた船をどうしますか」
このテーマでのディベートを授業で行って、
子どもたちからは、保存派、撤去派の両方の意見が活発にされたとのことでした。
これはこれで大事なことだと思うのですが、
自分としては、案外予定調和的な二つの議論になりがち、と感じています。
ディベートは、立論やプレゼンを楽しむゲーム的な意味が本来あるのだと思います。
しかしながら、日本の教育現場では、
どうしても、「どちらが正しいか」あるいは「どちらであるべきか」という結論になりがちです。
そして、冒頭のテーマだとすると、
先生のまとめが、『どちらの方の立論がロジカルで説得力があるか』ではない話になりがちです。
「どちらももっともな考え方ですね」
「お互いの意見を尊重しましょう」
「考えを深めるためにはもっと勉強しましょう」 みたいな、まとめが多いものです。
となると、子どもたちの中で今一つ突き抜けた発想が出てこない気がしてならないのです。
そして、この種の問いは、
世の中ではどちらでもよい、では済まされません。
『何らかの答えが必要』となります。
対立する考え方のどちらかを選ぶのか、
少しずつ譲り合って歩み寄るのか、
違う考え方をとるのか、といった「折り合い」をつける力が求められているのではないでしょうか。
私の考える21世紀型教育では、
冒頭の問いを「プロジェクト」ととらえています。
そして、この「プロジェクト」を解決しようとする学習を、PBL(プロジェクトベースドラーニング)と考えます。
さて、話をリハーサルに戻します。
「○○先生、この船のディベートは、ここで終わらずに一歩踏み込んで両者に折り合いをつけさせたら面白いのでは」
とついつい思索に入り込んだら、言葉が出てしまいました。
そうすると、この話の担当の若手の先生が素晴らしい反応をしてくれたのです。
「あ、なるほど。そうですね。早速授業でやってみます」と。
授業で実践したところ、とてもいい反応だったようです。
そして、いよいよ説明会。
若手の先生のスピーチに対して、保護者の方が大きな拍手をしてくれました。
小学校の教育。
まだ自分自身未開の地ではありましたが、何か大きく心を揺さぶられた瞬間でした。
こうして香里の丘の魔力が自分の中に刺さっていくのです。
・・・「香里ヌヴェールの挑戦」(第4回)に続く
「香里ヌヴェールの挑戦」(第1回)はこちら
「香里ヌヴェールの挑戦」(第2回)はこちら