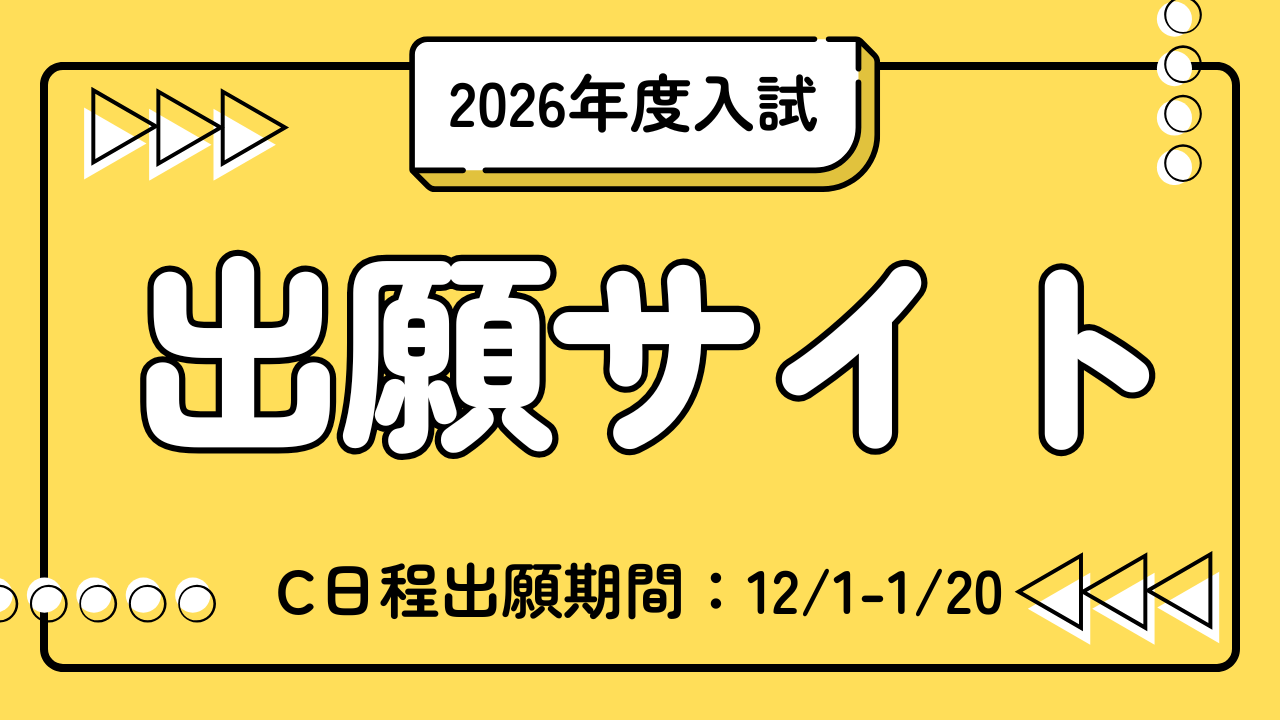2025.06.18 │4年 4年生 関西電気保安協会 電気の出張授業
4年生の理科では、電気のはたらきの単元を学習しています。普段の授業では、かん電池を使った実験キットを使って、かん電池のつなぎ方を考えたり、電流計で電流の大きさを調べたりしています。
今日は関西電気保安協会の方々にお来しいただき、備長炭を使った電池作りの体験を行いました。
「炭が電気を通すの?」「どうして電池がなくても回路が作れるの?」と子どもたちは興味津々。先生のお話に真剣に耳を傾けています。

さっそく、実験のスタートです。まずは細長くカットされた備長炭にキッチンペーパーを巻き、さらにその上からアルミホイルを巻いていきます。次に炭が見えている黒い部分と、アルミホイル部分の2か所に導線を巻きます。そしてプロペラをモーターに取り付けて、備長炭電池とつなげれば、回路の完成です!

しかし、この段階ではどの児童もプロペラが回っていません。「やはり炭は電池にならないのでは?」「どうしたらいいの?」と頭を悩ませていたその時!先生が炭に「魔法の水」を染み込ませてくださいました。すると、あら不思議。さっきまで止まっていたプロペラが勢いよく回りだしたのです。



「ええ?なんでー?」「すごーい!」と、あちこちから驚きの声があがります。
この魔法の水の正体はなんでしょう。消毒液だ!砂糖水だ!塩水だ!と色々な意見が出ました。正解は、なんと「塩水」です。海水よりもっと濃度の高い塩水を炭に染み込ませると、電気分解が発生して電気が通るようになるそうです。備長炭が立派な電池になるなんて、理科って面白いですね。


楽しい実験を通して、「電気について今まで以上に興味がわいた!」「お家でもやる!」と話す児童が多くいました。今日の経験が、理科の面白さや奥深さに気づくきっかけとなってくれれば嬉しいです。